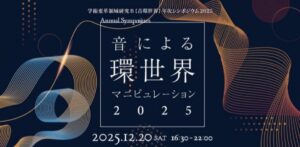A01 山内さんと各班代表による共著論文が国際学術誌「ACM Transactions on Computing for Healthcare (医療コンピューティング学術誌)」に採択されました
山内由大(A01班メンバー/善甫研M2)、井野敬子(総括班/A02班代表)、坂口昌徳(総括班/A03班代表)、善甫啓一(総括班/A01班代表)が、"Development and Evaluation of an Auditory VR GenerativeSystem via Natural Language Interaction to Aid Exposure Therapy for PTSD Patients"という題目で ACM Transactions on Computing for Healthcare(ACM HEALTH)に採択されましたのでお知らせいたします。ACM HEALTHは、 コンピューティングがヘルスケアをどのように改善しているかに関する科学的および技術的な結果を含む、高品質のオリジナル研究論文、調査論文、チャレンジ論文を発表する学際的なジャーナルです。2024年にはMedicine(Miscellaneous) カテゴリでCiteScoreトップ10%にもなっている非常に影響力の強い学術雑誌と言えます。
「Development and Evaluation of an Auditory VR Generative System via Natural LanguageInteraction to Aid Exposure Therapy for PTSD Patients」は、『音を活用したPTSD治療』に焦点を当てた研究であり、音による環世界のマニピュレーションの基盤をなすものです。本研究が取り組むPTSD(心的外傷後ストレス障害)は、命の危機などのトラウマ体験をきっかけに、その記憶に関連する状況やイメージに対して強い恐怖反応を示す、生活に支障をきたす精神疾患です。治療法として、恐怖の対象となる状況やイメージに触れさせ、段階的に慣れさせていく「エクスポージャー(暴露)」が非常に高い効果を持つことが知られており、国内外の多くのガイドラインにおいて推奨されています。しかしながら、この療法を実施するには、患者にとって適切な恐怖刺激となる状況やイメージを慎重に設定・計画する必要があります。例えば、患者が治安の悪い地域に居住している場合などには、安全性を確保できず治療を延期せざるを得なかったり、付き添いの人物を必要としたりするなど、環境設定が困難になることも少なくありません。また、イメージへの暴露を行う場合には、治療者が患者の苦痛の程度に細心の注意を払いながら、患者が言葉にできていない記憶や感情についても丁寧に引き出す必要があり、高度な技能と慎重な対応が求められます。これらの困難から、その治療効果とは裏腹に実際の臨床現場では十分に活用されていないという課題が存在するのが現状です。この課題を解決する手段として、近年ではVR技術を用いて恐怖対象を提示する「VRエクスポージャー療法」の研究が進められています。私たちは、その中の立体音響を活用したVRエクスポージャー療法という未踏領域にいち早く着目し、その可能性を切り拓く研究に挑戦しています。A02班では、持続エクスポージャー療法の一環として、患者一人ひとりに最適化されたテーラーメイドの音VRを提供し、治療への応用が試みられています。また、A03班では坂口が、トラウマ記憶の賦活化を目的に、睡眠時に音VRを提示するという新たなアプローチを模索しています。しかし、本研究において提案する音VRを活用したエクスポージャー療法を行うにあたり、我々はある1つの課題に直面をしています。それは、テーラーメイドの音VRの制作に時間がかかること、さらに音が「見えない」メディアであるため、完成までに複数回の修正ややり取りが必要であり、制作に数週間を要する点です。本研究では、生成AIと音のデータセットを組み合わせた提案システムによって、これらの課題を解決することを目指しています。本システムは、音響に関する専門知識がなくても、自然言語によるインタラクションだけで、希望するシーンを再現した音VRを生成することが可能です。このことにより、精神科医や心理士といった治療者自身が本システムを直接操作することができるようになります。サウンドエンジニアを介さずに短時間での修正や繰り返しの調整が可能となるため、治療者自身が治療的と判断する音VRを、迅速かつ柔軟に作成することが可能です。本論文では、提案システムのプロトタイプを実際に構築し、その有効性について検証を行った結果を報告しています。
本研究は、我々の研究チームの主題である「音による認知の操作」を活用し、実臨床においてPTSDに苦しむ多くの人々を救う効果的な治療法を提供するための、新たな治療開発に向けた極めて重要な第一歩であると考えます。今後も引き続き研究及びパブリケーションを進めて行く覚悟です。本論文の著者である山内、井野、坂口、善甫、そして我らが研究チームのさらなる活躍に乞うご期待ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。次の成果報告のお知らせでお会いしましょう。それでは、また。
科研費 学術変革領域研究B [音による環世界マニピュレーション] A01班メンバー 山内由大
山内由大
2024年に筑波大学で工学の学士号を取得し、筑波大学学長表彰を受賞しました。現在は、筑波大学大学院システム情報工学研究群に在籍し、空間音響や自然言語を用いたヒューマンコンピュータインタラクションに関する研究に取り組んでいます。

井野敬子
国立精神・神経医療研究センターにて、摂食障害やPTSDの臨床と研究に取り組む精神科医です。認知行動療法も専門としています。また、PTSDに対する認知行動療法のひとつである持続エクスポージャー療法の認定コンサルタントとして、治療者の育成をしています。

坂口昌徳(さかぐち まさのり)
筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構(WPI-IIIS)の准教授であり、睡眠と記憶のメカニズムに関する研究を行っています。特に、成体脳で新生するニューロンが睡眠中の記憶固定化に果たす役割や、PTSDの新たな治療法開発に取り組んでいます。光遺伝学やリアルタイム神経活動モニタリングなどの先端技術を駆使し、基礎研究と臨床応用の橋渡しを目指しています 。

善甫啓一
2008年に筑波大学で学士(理工学)、2010年にMBA、2013年に博士(工学)を取得しました。現在は、筑波大学の准教授であり、科学技術振興機構(JST)のさきがけ研究員、そして株式会社Xtrans techの代表を務めています。音響技術を軸に、人間の知覚の拡張や感覚の主体性、テレプレゼンス、XR、サービスの計測などに関心を持って研究しています。